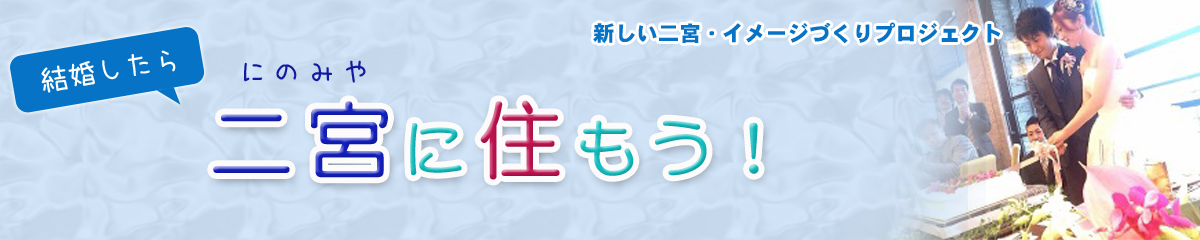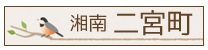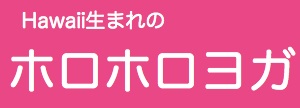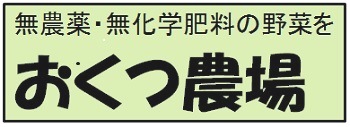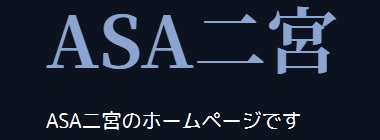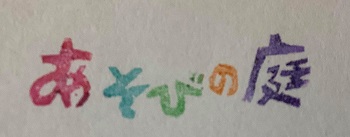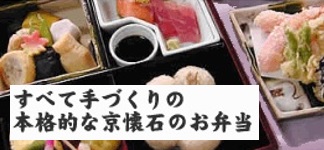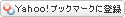にのみや どろんこLife
にのみや どろんこLife
蔵門の「にのみや どろんこLife2」


「農ある暮らし」をライフワークにされている蔵門さんに、2016年からコラムをお願いしています。
毎回興味深いテーマがたくさんありますので、バックナンバーもすべてお読みいただけるように編集しています。
vol.29「ボーっとする時間」
昨日までの予報が外れて、雨音で目を覚ました朝。「むむむ」と言いながら窓を開けると、天使がパタパタと飛んできて目の前に一枚の羽根を落として去っていきました。驚いてその羽根を拾うと、「ボーっとする時間」の文字。あらら、時間、拾っちゃいました。ひとまず、今日の仕事(造園業)を雨で中止する旨をお客様に伝え、山積する問題・課題は冷暗所(この時期、腐るといけないので)に押し込んで蓋をしました。少なくとも今日半日は神様からの贈り物としてこの時間、ありがたく頂戴することにいたします。
降って湧いたようなこんな時間は、台所で野菜を刻みまくり常備菜を作るのが常なのですが、御用聞き天使さんが届けてくれた羽根の意向を汲んで、今日は窓辺の椅子で雨に煙る吾妻山を眺めることといたしましょう。
ふと見ると、目の前の屋根の上にイソヒヨドリ。獲物を狙っているとか縄張りを主張しているとかの緊張感は微塵もなく、雨に打たれながら「ボーっとしている」感じで止まっています。いつも賑やかにおしゃべりしている鳥とはまるで別鳥のようです。じっとしていたかと思うと、時々方向転換をしたり、首をかしげてみたり、空を見上げたりする動きが私の視界に入り、山を眺めているはずが鳥の一挙一動を見守る形になってしまいました。イソヒヨドリと私の対峙は我慢比べのように、先ほどから20分以上続いています。困った。「お~い、こちらがボーっとできないぞー」
長らくこの原稿を書けなかった理由をいつもなら色々御託を並べるところですが、今回はもう連載をやめてしまったのかと思うくらい間が空きました。なので、その時その時あったであろう理由を、すっかり忘れてしまい並べることすらできません。(と、言いつつ)半年ほど前、頭を強打する事故があり、精一杯リハビリに努めたのですが、文章のキレのなさ、笑いの甘さは恐らくその後遺症かと思われます。何卒、広い心で見守りくださいませ。
いかんせんネタも切れ気味ですし、このままフェードアウトという選択枝もあったのですが、どうしても頭に引っかかっているネタだけは吐き出しておきたい。そうでなきゃ折角浮かんだネタが浮かばれない。その一心で今回もペンをとらせていただきます。
突然ですが、チャドクガという蛾をご存じでしょうか。ツバキやサザンカの葉の裏に、びっしり行儀よく整列している毛虫、その毛虫の親がチャドクガです。虫嫌いの方には申し訳ありませんが、今回はちょっとその蛾のお話。
春と夏、成虫が産み付けた卵が孵って、うじゃぁと毛虫が葉を埋め尽くし、この世の物とは思えない光景を作り出します。その毛虫の全身を覆う毒針毛が我々人間の皮膚に触れる(接触だけでなく飛散もあり!)と皮膚炎をおこし、猛烈なカイカイ症状を引き起こす非常に嫌われる虫でもあります。(その皮膚炎を起こすと、基本、気合だけで治す私は完治まで1週間ほどかかります。)
植木屋歴25年、毎年何度も何度も、奴らと戦ってまいりました。そんな植木屋の宿敵チャドクガが昨年からパタッと姿を消しました。昨年は「え?チョー、ラッキー!」くらいな感じだったのですが、今年は「もしかして絶滅!?」と思えるくらい遭遇しません。風通しが悪く葉が込み入っている、奴らが好みそうな環境下のツバキも、何故か正義感に燃え、しらみつぶしに探してみたのですが、一匹も発見できませんでした。
「♪それは、いい事だろう~?」という古い名曲の一節が頭をよぎります。植木屋仲間と話をしても「いやあ俺は絶滅してもらって全然オッケー、同情なんかするなよ~」と言います。蚊がこの世からいなくなって欲しいと常々、口走っている私ですから、虫差別になることはわかっていますが、内心「いや~、それまずいだろ~。」の気持ちでいっぱいです。以下、私の独り言。
・ひとつの種が絶滅したら、生態系ってどうなるんだろ?(チャドクガの幼虫はシジュウカラの好物らしいから、もしかしたら雑食性のイソヒヨドリも、それ、食べていたかもしれない。あの首傾げポーズは、いつものツバキに餌がないことに対する「はて?」だったのかもしれないぞ。)
・ひとつの種を絶滅させるほどの環境の変化っていったい何だろう?(直接間接問わず、おそらく人間が関わっているだろうことは察しがつく。私だって、気付かないところで関わっている可能性は十分にある。)
・ひとつの種が絶滅してしまい、自分よりも若い人たちに我々が宿敵と戦った話をしても、実物を見ることができないため、この恐怖の共有が永遠にできなくなるだろう。それは非常に寂しい。
やるかやられるかで戦うのは、人間を含む生き物の世界で宿命だとしても、絶滅はどうか避けたいと願ってやみません。我々植木屋にとって宿敵には違いないけど、同じ地球で同じ時を生きてきたものとして、できれば種をつなげてほしい。そう願ってやみません。
ここ数年肌に突き刺すような紫外線の変化とか、今回のようなチャドクガのこととか、植木屋だから切実に感じることがあります。「植木屋は見た!」ネタとしてどうしても書いておきたかったのでした。
滅多に書かないくせに書くと止まらなくなるクラモンです。今回も最後までお付き合いありがとうございました。
午後になっても、雨はしとしとしとしといい感じで降り続きます。イソヒヨドリはどこかの雨どいの中に潜り込んで、もう既に一杯やっているに違いありません。朝、届けられた羽根をもう一度手に取ってみました。イソヒヨドリの青い色がキラリ、光っていました。
(2024-7-21)

vol.28「身体の声を聞いてあげよう」
「そうか!この時間が足りなかったんだ。」あまりにも答えが身近にありすぎて、逆に新鮮な驚きです。お風呂の湯船にゆっくり浸かり、ぼーっと思考の栓を緩める時間。なんとまあ、久しぶりでしょう。
長すぎる夏は、風呂場をシャワーを浴びるだけの空間に変え、長湯する暮らしがあったことすら、すっかり忘れておりました。
このコラムの投稿が久しくご無沙汰なのは、根が真面目なワタクシですから、えー、えー、気になっておりました。しかし、溶け落ちそうな脳みそでは会話もままならず、発する声も言葉とは識別しがたい「わぁ~つぅ~い~(あつい)」を連発する日々。10文字以上の文章を書くなんて不可能に近かったと断言できます。そう、外仕事を生業にしている者たちにとって、この暑くて暑くて暑すぎた長い夏は、まさに地獄でありました。
ということで、ほぼ慣例となりました、投稿がご無沙汰な言い訳、かなりの行を使って綴らせていただきました。
長い夏のトンネルを抜けて、ようやく仕事以外にも体力を回せる自信が戻ってきた10月、久しぶりに秋山登山に行ってまいりました。テントを背負って山中3日の北アルプス。快晴の稜線をルンルン歩いて帰ってきました。
秋山とは言え、標高3000mくらいになると防寒着もかなり増え、ザックの重量問題が深刻になります。そんな中、食料計画は、遊び心、ご馳走心をそぎ落として最小限にせざるをえません。今回は泣く泣く、乾燥米(山菜飯、ピラフ)、乾燥ビーフシチュー、パスタ、インスタントラーメン、ビスケット、てなもので命をつないだ数日。
ちなみに私は菜食主義ではありません。ワインにステーキ、日本酒に刺盛、思い浮かべたらヨダレが出るくらいお肉もお魚も大好きなフツーの女の子(!?)。ただ、人と違うのは一食に占める野菜の摂取量が半端なく多いことでしょうか?いつも書くことですが、畑で採れてしまう大量の野菜を無駄なく消費するためだけに生きていると言ってしまえるくらい、何種類もの野菜を毎日どさっと体内に吸収する生活を20年以上続けています。前述の山の食事はもはや絶食に極めて近い絶野菜といっても過言ではありません。
準備のバタバタも含めて4日間、日増しに体調の変化を感じてはいました。絶食と同じ効果なのでしょうか。しだいに身体の声が聞こえてきます。最初のうちは遠慮がちに「えーっと、野菜、もそっとなーい?」から始まり、2日目には「すみません、いつものやつ、いただけません?」。3日目には「おら、おら、青いやつと黄色っぽいやつ、それからフレッシュ果物もってこんかいっ!」。身体の叫びがしっかり聞こえるから不思議です。
なんとか声の主をいさめながら、帰宅後、荷物の片付けも終わらぬうちに、需要と供給のバランスが崩れた畑へ走ります。こちらでも「おらおら、はよ、採らんかいっ。」とスゴんでる野菜たち(空心菜、つるむらさき、オクラ、シカクマメ、ナス、カボチャ、サツマイモ)を一目散で収穫して体に詰め込んであげました。ポパイのほうれん草(わっかるかなぁ)ほどの即効性はありませんが、じわじわ半日置きぐらいに身体に精気が戻ってくるのを実感。やがて「やいのやいの」とうるさい声は聞こえなくなりました。
自分の心と向き合うのは、案外コツがいるのかもしれないけれど、私の身体の声、めちゃくちゃシンプルです。
今日は、涼しいを通り越して、晩秋を感じさせる雨の一日。
今年初物の冬瓜を煮て、スープを作ります。
この夏は、人間だけじゃなくて、植物も昆虫も動物もみんな叫んでいたんだろうなあ。口から発した言葉以外の声は、耳を傾ける側の心の状態で聞こえたり聞こえなかったりするからね。
まずは、自分を整えなきゃです。
スープに入れるショウガを刻みながら、しみじみそんなことを思ったりするクラモンでした。
(2023-10-13)

vol.27「ふきの季節」
桜の花がちらほら咲き始めた頃、道端の無人販売所を通り過ぎようとして「あっ!」と振り返りました。「え~、もう、フキ~?」
♪「季節の変わり目さえ気づかない程、ぼんやりしているあなたに~」という歌があったなあ。
今さっきまで畑でくつろいでいた野菜たちが、お行儀よく並べられた一角から、その歌声が聞こえてくるようです。「フキだよ、フキ!フキの季節だよ~!」
無人販売所の野菜たちに、季節を気づかせてくれた感謝の一礼をしてその場を後にします。そそくさと向かった先は、まだ寒い2月、フキノトウを摘んで春の訪れを噛みしめていた畑の隅っこ。景色もすっかり変わり、葉を茂らせたフキたちがまだかまだかと待っていてくれました。
フキをとって持ち帰り、板ずり、下茹で、皮を剥き、油揚げと炊いて、おかずにします。多めに作って常備菜にするのですが、あっという間になくなるのでまた畑に向かいます。フキを摘む→油揚げと炊く→食べる→フキを摘む。果たしてこれを何回繰り返すことでしょう。おそらく初夏に入ってフキが固くなって歯に繊維が挟まるようになるまで、我が家の食卓にはフキが並び続けます。
そこまで執拗にフキを食べる理由が「ただ、好きだから」では言葉が足りない気がしています。
登山家の人に向けられた、なぜ山になぜ登るのか?という愚問に、彼らは決まって「そこに山があるから」と答えてかわします。それに近いものがあるのですね。「そこにフキがあるから。」
★
フキを食べ続けるこの時期に必ず思い出すエピソードがあります。
昔話で恐縮ですが、青森の津軽半島を相棒と二人で自転車をこいでいた時のこと。日没までに麓の集落にたどり着けないと判断した我々は、峠道の空き地に野営をすることに決めて、まだ陽のあるうちからテントを張る準備をしておりました。
そこへ、地元の軽トラが止まり、中から出てきたばあちゃんとその孫らしき子供に声を掛けられました。
「おめ~ら、ミズ、知ってっか?」首を横に振ると、「ついてこい」と先を歩き、さっさと山に分け入っていきました。沢の近くでしょうか?鎌を取り出しこう言います。「こうやって、摘むだ。さあ、摘め。」
ばあちゃんと孫と、旅人二人で30分ほど収穫したでしょうか。テントに戻ると、こんどは「おめ~ら、湯沸かすもん、あっか?」。
言われるまま、鍋にコンロで湯を沸かし、指示を仰ぎます。口数の少ないばあちゃんは、今、取ってきたばかりのミズを湯がいて、皮を剥き「じゃあな」と孫を連れて帰っていきました。四人で採ったミズは全部くれました。醤油があれば良かったのだろうけど、夕飯はそのミズに塩をかけていただきました。
あの、ばあちゃんにはもう会えないだろうけど。あん時の、ミズ(ウワバミソウという山菜ですが、形態は極めてフキに近いです)。一生、忘れられません。もう一度、食べたいなあ。
そうそう、この話にはオマケがあって、夕餉を終えて、寝袋の準備をしていると、また別の軽トラが止まって、おじさんが下りてきて言いました。「おめ~ら、ブヨ、気をつけろ。」キンチョールの缶を置いて行ってくれました。そのあと、暗い山道、車は一台も通らなかったなあ。そのくらい人里離れた場所で受けた人情でした。
津軽の言葉が悲しいくらいに聞きとれないし、口数も少ない人が多くてね。それなのに、もしかしたらそれだからこそ、心の奥底にぽっと火を灯してくれたのかもしれません。そしてじわじわ、こんな風に一生、温め続けてくれるんですね。
そんな昔話を思い出しながら、今日もフキを炊いています。
★★
数日前、近所で若い畑女子2人と立ち話していた時ね。
「クラモンさんって、以前、ブログ(どろんこLifeのこと)書いてましたよね。私読んだことあります。」Aさんが言いました。
それを聞いて私の眉が数ミリ、ピクリとしたのに気づいたのでしょう。隣にいたBさんが慌てて言いました。「今も続いてるよー。たま~に、更新されてますよね。」眉が更に数ミリ動いたのは、麦わら帽子の庇をさりげなくずらして、見られなかったようです。
はい、現在も継続中で、たまに更新しております。ちょ~ど、今、書こうかなあと思っていた所でした。
読んでくれたことがあると言ってくれた、ありがたい二人の言葉に背中を押されて、どろんこLife、まだまだ、しつこく続きます。
(2023-4-17)

バックナンバーはこちらからお読みいただけます
<にのみや どろんこLife2>
vol.26「ドキュメント吾妻山」

vol.25「夏はカブトムシ」

vol.24「ハカラメのススメ」

vol.23「ニンジン」

vol.22「哀愁のカネタタキ」

vol.21「うりっす!」

vol.20「干し野菜」

vol.19「夜咄の茶事」

私のような奴もいる
vol.18「蚊取り線香」

(Photo by m.o)
vol.17「枯れる」

vol.16「いわくつき野菜のすすめ」

vol.15「勝手に生えてる野菜の生命力」

vol.14「嵐の前の、春の日に」

vol.13「風邪っぴき」

vol.12「恩返し」

vol.11「実験!自然農法」

vol.10「三月のホタル」
vol.9「休眠期」

vol.8「ひっかかっているもの」

vol.7「どろんこLifeの始まり」

vol.6「イノシシ」

vol.5「きゅうり」

vol.4「わかりやすい顔」

vol.3「畑に向かう理由」

vol.2「“こぶし”とり」

vol.1「再びペンをとる」

<にのみや どろんこLife>
vol.15「さくら暦」
vol.14 「味噌の仕込み」

vol.13「佐島のわかめ」

番外編「パッションフルーツ その後」
vol.12 「ウコンのほりあげ」


vol.11 「パッションフルーツ」

vol.10 「田園の食卓」

vol.9 「野菜の癒し成分」

vol.8 「三大輪切王の季節」

vol.7「とうもろこし競争」

vol.6 「パンダなひとたち」

vol.5 「ジャガイモ収穫いとたのし」

vol.4 「ピヨピヨ」

vol.3 「玉ねぎの季節」

vol.2 「畑人(はたけびと)、走る!」

vol.1 「タケノコ!ごろりん」